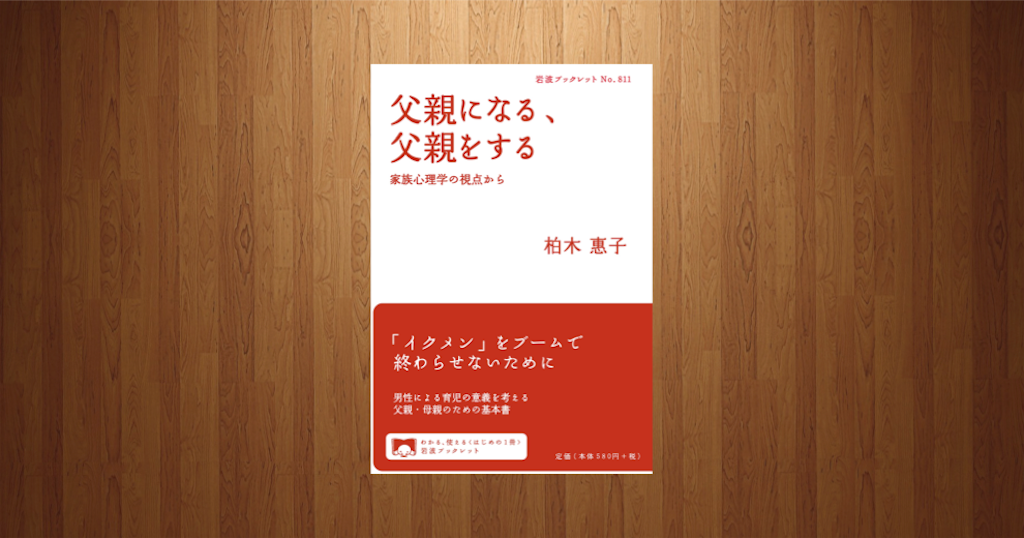
育児に悩める男性に、これから父親になる男性とてもおすすめの本を見つけました。
特に、「感覚として男性も育児参加しなければならない」と理解できるが、「男性が育児に参加しなければいけない理由」が明確にわからないという方におすすめの本です。
今回ご紹介するのは岩波ブックレット(発行所:岩波書店)の「父親になる、父親をする〜家族心理学の視点から〜」著:柏木 惠子です。
著者の柏木氏は「父親になる」のではなく、「父親をする」という表現で、男性の家庭進出について問題を提起します。
一方で、この本には具体的に男性が育児で何をすべきかはほとんど書いていません。データを用いて、現代日本の子育て社会への問題を提起しています。
この本を読めば「男性の自分が今、何をすべきなのか」というのを一層掘り下げた視点で考えることができるはずです。
パパになる人が絶対読むべき本【13選】プレゼントにも最適! - 男の家庭進出実践
父親になる、父親をする〜家族心理学の視点から紹介
こんな人に読んでほしい
- これから父親になるが、参考になる本を探している人
- 男性の育児参加を「感覚」で理解して「論理」で理解できていない人
- 男女は生物学的に違うから女性優位の子育ては仕方ないと思っている人
- 日本のどこに育児の問題点があるか、わからない人
この本の難易度・読了までの時間
72ページの本なので、30分〜2時間程度で読めるでしょう。
私はコインランドリーの待ち時間45分で読み終わりました。
この本は、グラフデータを交えながら、比較的わかり安い言葉で書かれているので、そこまで難易度は高くないです。
ただし、パパのハウツー本とは少し毛色が違い、若干の学術論文的記載もあります。
大学で論文執筆の経験ある人なら余裕で読めるでしょう。
この本の見所
この本のサブタイトルは〜家族心理学の視点から〜となっています。
内容としては心理学だけでなく、世界の育児事情の比較から、日本の子育ての問題点を客観的に紐解いています。
この本のみどころを各章からご紹介します。
父親になること、父親をすること
人間の場合、「親になる」だけでは、子どもに対する親の役割を終えることにはなりません。(中略)誕生した子を育てること、すなわち「親をする」ことが必須となるからです。(父親になる、父親をする P.5)
人間は他の動物とは違い、「親をする」すなわち、子育てが必須ということです。他の動物のこどもは生まれてからすぐに自分で歩き、エサを探し、すぐ「一人前」となります。
人間が肉体的・精神的・社会的に「一人前」になるまでには「親をする」という行為が不可欠なのです。
動物ではメスだけが「親をする」のが当たり前なのですが、オスが子育てをする例外的な種があります。サルの仲間のマーモセットです。(中略)マーモセットだけではありません。子育てのコストが大きい場合-例えば、仔がたくさん生まれる、エサが乏しい、外敵が多いなど種では、オスも子育てをして、繁殖を成功させています。(中略)このようにみてくると、人間の場合も同様であることが理解できるでしょう。(父親になる、父親をする P.13-P.14)
「親をする」という行為が必要な動物の大半はその役割をメスが担います。しかし、子育てのハードルが高い種ほどオスの子育て参画が必要不可欠なのです。
そして、人間もそのうちのひとつの種です。
第1章の「父親になること、父親をすること」では、われわれ男が「なぜ、男(オス)の育児が必要なのか」ということを生物学的観点で理解することができます。
父親たちは、いま
夫の子育てについて妻たちがどのように語っているかを調べた研究から、(中略)次の三つの特徴が指摘されています。すなわり、①受動的な子育て、②趣味・楽しみみとしての子育て、③"いいとこどり"の子育て、です。(父親になる、父親をする P.25)
例えば、
①食器洗いや洗濯などの家事を妻に「言われてやっている」
②お風呂に一緒に入るの(=自分にとっての楽しみ)は積極的にやっている
③夜中に起きた子どもの寝かしつけは(母乳じゃないと寝ないからなど、理由をつけて)妻に任せている。
などの行為は、妻から見たら批判の対象となるのですね。
子どもとポジティブな関わりをもつことがマイナスの評価になることはよくないと思いますが、その関わり方の"質"が問われているということです。
父親として育つ時とき
女親か男親ではなく子育ての責任をどのような立場で担っているのか。つまり、子育ての第一責任者なのか、二番手かなのかによって、子どもへの行動や感情はちがってくるとみることができるのです。(父親になる、父親をする P.17)
第1章での上記の記載をうけて、第3章では下記のように語られています。
子育ての第一責任者となった父親は、最初は家事や子育てに振り回されていたけれど、次第に大変さよりも、工夫するこのおもしろさや、その工夫がうまくいった時の達成感などを発見したといいます。(父親になる、父親をする P.55)
父親が育児をする上で、この本を読んで大事だと感じたことはこの部分です。
つまり、「父親」として子どもと接するという意識から脱却し、「第一責任者」と意識で子育てをするのが理想なのではということです。
先日、パパ友から相談を受けました。
「言ってくれれば何でも手伝うから、やって欲しいことがあれば言ってね」といつも言っているのに、妻の機嫌がなおらない、と。
彼の場合は海外単身赴任中で、一時帰国の時しか育児に携われないというビハインドはあるのですが、そこに決定的に足りないのは「第一責任者」としての意識です。
「父親になる」のではなく第一責任者の意識で「父親をする」ことの重要性がこの本から伝わってきます。
まとめ
この本では「父親が育児で何をすべきか」ということはほとんど書かれていません。
しかし、確実に父親としての意識を変えてくれるでしょう。
そして、世界的にみたときの日本の男性の育児参画・家庭進出のレベルの低さにも愕然とするはずです。
その事実を知った上で、自分は何をすべきか、自分の頭で考えて行動するための一冊でもあるでしょう。
男性にかぎらず、女性にも読んで欲しい一冊です。
父親になる、父親をする〜家族心理学の視点から〜目次
第1章 父親になること、父親をすること
- 人間だからこそ必要な子育て
- 子育てを可能にする人間の「心」
- 養育するのは親だけではない
- 「進化の産物」としての父親
- 父親と母親は違うのか?
第2章 父親たちは、いま – 日本の現状をみる
- 「イクメン」というけれど
- 問われる子育ての中身 – 父親にとって子どもとは
- 子ども中心家族か、夫婦中心家族か – 子どもの誕生と夫婦関係の変化
第3章 父親として育つとき
- 妻は夫をどうみているか
- 子どもにとって父親の意味とは
- 父親として成長するために
終章 父親をすることが可能な社会へ
参考:2011年初版
2011年6月 第1刷発行なので、執筆時点ではすでに7年前となります。
2011年というと、前年の2010年には「イクメン」が流行語となった年ですので、社会的関心が高まっていた時期に執筆された本です。
そんな時代に執筆された本ですが、7年経過した今でも普遍的な記述がいくつもあり、気づかされる事が多くあります。
7年経過した現在でも、現状として大きく変わったということはないかもしれませんが、しかし少しずつ変化していることもあります。
例えば、この本の執筆時(平成21年)で、男性の育児休暇取得率は1.7%となっていますが、平成27年のデータでは2.65%まで上昇しています。
ただ、大きな観点で見れば世界からみた日本の男性の育児の現状はそう大きく変わっていません。
今読んでも、大きな気づきが得られるでしょう。